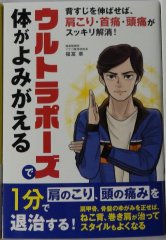福富健康院/マサゴ整骨院 | 日記 | 関ケ原の戦い
福富健康院/マサゴ整骨院 日記
TOP > 福富健康院/マサゴ整骨院 日記 > 関ケ原の戦い
関ケ原の戦い (2010.01.20)
◎竜馬伝 と江 姫たちの戦国~
竜馬伝が終了して、来年は、『江 ~姫たちの戦国~』 が始まるらしい。
タイトルから察するに、お市の方の娘、浅井三姉妹の物語でろうが、
時代を超えて竜馬の時代に繋がっている。
キーワードは〝関ヶ原の戦い〟
竜馬をはじめとする討幕に動き、新しい日本を造ろうとした人たち・・を生んだ
所謂、薩・長・土・肥は、関ヶ原の戦いにて西軍について、所領を没収または減封されたり、斬首にあった大名の領土であったところである。 ※薩摩は例外的に本領安堵
一旦は所領安堵を約束されたものの反故された、毛利をはじめとして、関ヶ原の戦いの
残した遺恨の念は、何百年もくすぶっていた訳である。
竜馬伝に出てきた、下士という人達は、関ヶ原以前に土佐の領主であった
長宗我部氏の家臣が多く、山内家の家臣である上士に虐げられていたのは、ドラマの如くである。
浅井三姉妹― 長女 茶々は秀吉の側室となり、豊臣の跡取りとなる秀頼を産む。
次女 初は京極高次の妻となる。
三女 江は二度の結婚・離別ののち、徳川秀忠の妻となる。
関ヶ原の戦いの時三姉妹は・・・
茶々は、淀殿として、大阪城にて幼い秀頼の傍らにいて、豊臣の天下を脅かす徳川家康を
西軍が滅ぼす事を願っていたはずである。
江は、関ヶ原の戦い の数年前に、秀忠と結婚。
秀忠は、信濃上田城の真田昌幸・幸村父子の抵抗に合い足止めされた事により、遅参する。
問題は、初の嫁いだ京極高次である。
高次は、三成挙兵後に、大谷吉継らと同行し、西軍に従っていたが、途中で居城である
大津城に立て籠もり、西軍を大津で足止めした。高次に徳川の味方をするように助言したのは、お初であったと言われる。
動向不明瞭な毛利家にあって随一の主戦派であった毛利元康や名将として知られた
立花宗茂の一万五千の西軍を決戦の当日まで引き留めた。
もし、この軍が 関ヶ原本戦 に間に合えば、家康は相当苦戦させられたであろう。
更に、大阪城の秀頼の許にいた淀殿のショックは大きかったであろう。
妹婿にあたる 高次が寝返った事の精神的ダメージに加え、関ヶ原への
行く手が阻まれた事で、勝利への〝切り札〟である秀頼を出陣させられなくなり、西軍の総大将・毛利輝元も秀頼をお守りする事に徹せざるを得なくなったのである。
輝元が秀頼を従えて出陣しておれば、秀忠率いる徳川本隊が遅参し、豊臣恩顧の大名で戦わざるを得なかった 東軍は、福島正則、加藤嘉明などは、西軍に槍を向ける事は出来ず、その結束は乱れたと思われる。
つまり、この時点で、家康軍の勝利は、グッと近づいたのである!
◎関ヶ原の戦い―東・西どちらにつくか その1
竜馬伝をみていると、
〝討幕により今までの身分制度を壊し、新しい世の中をつくる〟という人々と、
〝今の保証された身分を堅持したい〟という、現状維持派の心中が良く描かれていて
とても興味深かった。
関ヶ原の戦いも、能力のある者がのし上がれる、自由な世の中を信長・秀吉路線を継承していく『三成派』と、 戦国の世を終わらせて、安定した世の中をつくろうという『家康派』の戦いであったはずである。
しかし、徳川家康により、徳川と石田の私戦にすり替えられ、戦によって功をたてて、武力によって地位を築いてきた、政治力より武力重視の〝武断派〟を味方に引きずり込んだのである。
ましてや、彼らは、豊臣恩顧の大名で、家康方には本来つくはずがない面々である。
関ヶ原の戦いは東・西どちらにつくかの、究極の選択であり、お家の存続に係るものである。
戦後にそれぞれの大名家がどうなったかという事実をみると、
その選択がいかに厳しいものであったかが解る。
そのなかで、豊臣政権下で、家康に次ぐ大大名である毛利家もその選択をせまられていた。
そして、毛利輝元は西軍の総大将となる。
毛利は、中国の覇者としての現状維持を図りたいというのが、目標であったと思う。
家康について、勝利を勝ち取っても、二番手どころか目の上の瘤となり、
前田・上杉のように、難癖をつけられて失脚するのは目に見えており、小大名である石田について、その後の政権の要職に就き、実権をにぎり、力を揮うことを選択したと思われる。
担がれて総大将になったといわれるが、毛利が今の地位を維持できるのは、この選択しか
なかったのかも知れない。
しかし、小山評定にて、豊臣恩顧の大名をはじめ、上杉征伐に赴いたほとんどの大名が、東軍につくことを表明する。
これにより、江戸より東海道のほとんどの大名が東軍となり、家康の進軍は極めて楽になった。
そして、西軍の織田秀信の居城である岐阜城がわずか数日で陥落。
信長が要塞とした、名城を攻略した事で、流れは一気に東軍に傾いた。
そこで、毛利は思い切った策に出る事になる。
◎毛利のお家事情
毛利家には三枚のカードがある。
毛利輝元・安国寺恵瓊・吉川広家である。
毛利元就の頃には、毛利宗家を小早川・吉川の 毛利両川 が支えたが、
小早川秀秋は、豊臣秀吉の養子であったが、側室淀君がお拾いを産んだため、小早川家に半ば押し付ける形で養子に出された経緯で、毛利との繋がりは薄い。
実は、小早川隆景に実子がなく、元就の九男・元総を小早川秀包を養子としていたが、
秀秋が小早川に入った事により、養家を出されている。
毛利家の内情としては、安国寺恵瓊と吉川広家は、犬猿の仲で一枚岩にはなっていなかったが、輝元を支え毛利を盛り立てようという心意気は双方共に持っていたと思える。
安国寺恵瓊は、毛利の使僧として羽柴秀吉の備中高松城水攻めの際に講和成立に働いた事にはじまり、常に豊臣と毛利の間をとりなしたことにより秀吉の信任をえており、石田三成とも親しかった。
朝鮮出兵の際、豊臣の奉行として参加して、吉川広家の抜け駆けの功名を非難して秀吉に報告しなかった事より険悪な関係となった。
逆に、広家は、文禄の役の際に、福島正則、黒田長政、加藤清正らの武断派と親しくなり、特に黒田父子とは入魂の仲であった。
吉川氏は、元春の時、秀吉に五大老に抜擢された小早川隆景に対抗意識を持ち、以後も反りが合わず、特に隆景と親しい恵瓊を目の敵にしてきている。
毛利が三成派と家康派に分かれていたという事は、逆にいうと、どちらにも太いパイプを持っている事になる。
毛利は、先ず1枚目のカード〝安国寺恵瓊〟を切って、石田三成・大谷吉継と謀り、毛利輝元を西軍の総大将として大阪城に入城させた。
そして、豊臣恩顧の大名の殆んどが徳川方に就いたという情報が入り、黒田長政を通して徳川と内通すべく吉川広家という2枚目のカードを切る事になる。
そして、関ヶ原の戦い前日、毛利家家老、福原広俊と相談の上、人質2人を戦闘不参加の書状と共に長政に送り、輝元の無罪と領国を保証する盟約をとりつける。
勿論、「輝元は、家康に刃向う気も天下を望む気もなく、恵瓊に担がれただけ」というのは、苦し紛れの弁明であり、大阪入城当時は、天下とまではいかずとも、豊臣政権下で実権を握る野望は持っていたと思われる。
しかし、2枚目のカードを切った事で、3枚目は切られる事無く、〝大阪城にて、ただ秀頼公をお守りする〟という形で、関ヶ原合戦を迎える事となる。
◎南宮山動かず その1
まず、関ヶ原の合戦当日の 毛利軍の動をみていく。
大将 毛利輝元は大阪城西の丸にて秀頼公のもとを動かず、毛利元康(元就八男) と
小早川元包(元就九男)は、前日まで家康方に寝返った 大津城包囲攻撃にて足止めされている。
そのほかの武将は関ヶ原本戦に陣取りをしていた。
毛利軍は、関ヶ原の東西の両端の松尾山、南宮山に陣取りをしている。
松尾山には小早川秀秋の一万五千、南宮山山頂には、毛利秀元の一万二千、
その後備に安国寺恵瓊の千八百、南宮山の前方の山麓には、吉川広家の三千三百が陣取っている。
どちらからも、関ヶ原の盆地が一望できるロケーションにあるが、戦うには山を下りる必要があり、かなり不便な場所である。
この南宮山には、五奉行の一人である長束正家千五百、南宮山のさらに南の栗原山麓に長宗我部盛親の六千六百も陣を構えている。
関ヶ原の本戦は、結果的に、この毛利勢の動向が勝利を決したのであるが、実は、この陣取りをした時点で、徳川の勝利は決まっていたといえる。
私がそう思うのは、キーマンとなった小早川秀秋と吉川広家の立場に立って考えた時、そう考えざるを得ないからです。
小早川秀秋は、色々な事情から徳川側に寝返る約束を取り付けていていた訳だが、もし、西軍として山を下りるとしたなら、圧倒的な有利を確信できた時のみ、つまり、南宮山の吉川・毛利が西軍として山を下りて家康軍と戦った時のみと思われる。
逆に、毛利隊を動かさず、毛利不戦を条件に本領安堵の約束を取り付けている吉川広家は、万が一、西軍として山を下りて家康軍と戦うとしたなら、圧倒的な有利を確信できた時のみ、つまり、松尾山の小早川秀秋が山を下りて家康に刃を向けた時のみと思われる。
吉川広家も、目的は毛利の存続・所領の現状維持であるので、その万が一の時の為に、傍観軍として南宮山に陣取りをしていたものと思われる。
秀秋は、元々 三成に朝鮮の役の失態を咎められ、減封・転封された時、家康がとりなして旧領に復帰できた経緯、黒田長政が内応の約束を取りつけている事の他にも、伯母であり、育ての親である北政所から、家康についていく様にきつく言われた事情を知っており、十中八九家康に付くと思ってはいたが、その若さ故、好条件を提示しての三成の誘いに心を動かされることも否定できなかった事情があった。
◎南宮山動かず その2
松尾山の小早川勢も、吉川広家が家康に内応して、毛利を動かさない約束をしている情報は、黒田長政から聞かされている。
しかし、毛利秀元が同じ南宮山の背後に陣取っている、安国寺恵瓊や長束正家に説得されて山を下れば、さすがの広家も止められないというケースも考えられる。
安国寺恵瓊や長束正家は、もし、毛利が中立を保って家康が勝利した時、自身の命が危うくなる立場にある為、必死の説得をすると考えられる。
実際、吉川広家は不戦を貫くという奇妙な戦いを強いられる。広家自体は、小早川秀秋が松尾山を下りて家康と戦う事態になった場合以外は、南宮山から兵を下りさせないつもりでいた。
合戦開始から激しい戦いが繰り広げられ、宇喜多隊・大谷隊・石田隊・小西隊の活躍でやや西軍が押し気味で戦いを進めている。機が熟したとばかりに、石田三成が陣をしく笹尾山から狼煙があげられたのが確認できた。
狼煙の合図に、毛利宗家の軍を率いる毛利秀元は腰を上げて戦闘態勢に入ろうとしていた。
安国寺恵瓊、長束正家からも使者を通して再三に亘る出陣の要請が来ている。
秀元が先鋒の吉川広家に出陣の催促をするも、「出陣の判断はお任せあれ」と言って首を縦に振らない。
広家にとって、出陣の機が熟す時とは、秀秋が家康に向かって山を下りた時しか考えられない。
それ以外は、毛利の長老として、毛利の存続を図る為、一兵たりとも動かさぬようにするのが任と心得ているのである。
秀元は、安国寺恵瓊、長束正家からの使者に、「今、弁当を使わせている」という、俗に「から弁当」いわれている苦し紛れの言い訳をしていたといわれるが、さすがに立ち行かなくなり、自らも広家や福原弘俊の陣所に催促に赴いている。その時、弘俊から、事のいきさつを聞かされて愕然とする。
秀元は、剛勇で名を馳せた真直ぐな性格の若者であったと言われており、戦意は充分に持って布陣していたのである。実は、秀元は知行地をめぐり広家とは対立していた事もあり、強権発動して山を下りる事も考えられなくはなかったのであるが、大阪の輝元からは、「広家に従って、毛利家の為 尽くすように」と言われていた為、強行突破して動く事はなかったのである。
安国寺恵瓊も長束正家も、毛利本隊が動かない事には、どうする事も出来ず、催足を繰り返すしかなかった。
松尾山からは、関ヶ原の盆地を挟んだ東の端に、南宮山を望む事ができた。山を埋め尽くしている戦旗は、戦局や陣営の動きを知る事ができる。
しかし、使者が動くと思われる位のわずかな動きの他には、大きな動きは見られない。
「やはり侍従殿は、動かないつもりのようであるな」と、秀秋は、ほっとしたように側近の平岡頼勝と稲葉正成に
言った。毛利の宗家も、黒田長政が仕組んだ東軍への内応の手筈通りの傍観に徹しているようである。
秀秋も、家臣たちも、腹は家康に味方することに決まっていたが、裏切りという行為に踏み切る後ろめたさが、山を下りるのを踏みとどまらせていたから、この毛利の行動は心強く感じられたのである。
◎南宮山と松尾山
毛利勢は、まず安国寺恵瓊に交渉に当たらせ、毛利輝元を西軍の大将として、西軍勝利の際には豊臣政権下において執権の座に就く腹づもりであった。
小山評定において、豊臣恩顧の大名のほとんどが、家康に付いた事、岐阜城が東軍の手により陥落した事、
五奉行の1人、増田長盛の家康内応文書、大津城の京極高次が東軍に寝返った事により、高次の妻・お初の姉である淀殿が秀頼の出陣を見合わせた事等により、西軍の旗色が悪くなると見るや、黒田長政、藤堂高虎と親交が深い吉川広家を内密に交渉に当たらせた。
そして、毛利の家康に反抗する事が無い旨を伝えたうえで、関ヶ原本戦を傍観する事を条件に、領国安堵・毛利安泰の血判書を取り交わしている。
この場合、毛利輝元を西軍の大将に担ぎ出した首謀者として安国寺恵瓊は一人で責任を負う事になる。
恵瓊は、長束正家と共に、南宮山の岡ヶ鼻に別働隊の最後尾として布陣していた。
長束正家は、豊臣政権下において、五奉行時代から、大老・毛利輝元の連絡役としての結びつきがあった為、毛利に同調する形で南宮山後備に陣を敷いたと思われるが、秀元に出陣の催促をするも、
大阪にて動く気配が感じられない輝元に不安を抱き、強硬に動く事はできなかった。
恵瓊も、三成挙兵当初は、前面に出て輝元を総大将にする事に積極的に動いたが、西軍不利の情報が色々と伝えられた事で、毛利の主導権を吉川広家に移して、東軍内応の方向で進められていた。
南宮山において、広家を先鋒に、恵瓊を最後尾に布陣させた時点で、毛利軍のその動向は戦前より想像し得るものであった。毛利の方針が変わった以上、恵瓊としては、秀元に出陣催促をするも、強行突破はできず、傍観せざるを得なかったのである。
実際、大谷吉継は、南宮山の布陣を見た時、毛利の内応を察知していた様である。
三成も、兵馬の上り下りもままならない急峻な山への布陣に疑念を持っていた様である。
南宮山に何の動きもないのを見て取った家康は、本陣を前に進め、南宮山に備えていた後衛部隊、池田輝政・山内一豊・浅野幸長・有馬豊氏の陣を前に出させている。
この、後衛部隊の顔ぶれを見ても、娘婿の池田輝政や律儀な山内一豊を配している等、家康も、最初は南宮山の内応を確信してはいなかったと推測できるが、石田陣所からの参戦の合図の狼煙にも、動かぬ事に安心したのであろう。
松尾山においても、小早川勢が、南宮山の動かぬ状況と本陣・後衛部隊の前進する模様が遠望でき、毛利勢の家康内応を確信しつつあった。
その時、家康軍と思われる旗印が松尾山麓に向って来て、山に向けて射撃しているような硝煙が確認できた。
秀秋は驚いたというよりは、毛利勢の内応を確信して、毛利の一員として、家康に付いて行動を起こす踏ん切りがついた時にタイミングよく、催促ともいえる合図がなされた格好になったのである。
「家康殿にお味方する。目指すは、大谷吉継の陣なり」
秀秋の声が響いた。
◎敗走
松尾山の小早川軍は、大谷吉継の陣をめがけてなだれ込んだ。
吉継は、秀秋の裏切りを予測していた為、その時に備えた陣形をしいていた。
その為、秀秋隊は、2度3度と押し返された。
その時、藤堂高虎の旗の合図と共に、脇坂安治、赤座直保、小川祐忠、朽木元綱の四隊が一斉に、大谷隊に向かってきたのである。
これらの武将は、吉継の指揮下におかれ、松尾山の裏切りに備えて配置していた面々である。
さすがの大谷勢も、側面をつかれ、一気に戦況は悪化、主力の戸田重政、平塚為広も討たれ、壊滅状態に陥る。吉継は、混乱の中で自害。
大谷勢壊滅により、藤堂高虎、京極高知の部隊が矛先を小西隊、宇喜多隊に向けて押し寄せてくる。その勢いに押され、小西隊は、北国街道に敗走。
宇喜多隊と石田隊は、懸命に奮戦するが、敵軍に取り囲まれる状態になり、ついに潰滅。
南宮山からも、小早川の裏切りは遠望でき、西軍の戦況悪化の情報も伝えられてくる。
広家は、「やっと終わったな」と安堵の表情を浮かべた。
「これで、輝元殿も、毛利家も安泰であろう」
長政との約束を守り、南宮山から一兵たりとも山を下りさせなかった、その奇妙な戦いの成功に胸を撫で下ろし、南宮山を立ち去った。
主戦場では、島津隊が敵中突破を画策していた時、南宮山の各部隊は、それぞれの退却が行われていた。
吉川広家と福原弘俊は、家康軍に合流した。
対して、長束隊と長宗我部隊は、伊勢街道をめざして敗走している。
長束正家は、多芸口にて徳永寿昌、市橋長勝に攻められ、長宗我部盛親も、追撃を受け百十三名の将兵を失っている。
長宗我部盛親は、父元親の病死により、家督を継いで一年足らずにて、関ヶ原の選択を迫られ、毛利の大樹に寄り添う様な形で、南宮山のさらに南の栗原山の麓に陣を敷いていたが、主戦場から遠く離れているうえ、南宮山の様に眺望も効かず、戦況も把握できぬまま、敗戦の報を聞く事になる。
長束正家も、五奉行時代から、大老毛利輝元の連絡役を務める等、実務を通しての結びつきが強く、毛利の動向に合わせる形になったが、大阪を動かぬ輝元に対しての不安から、毛利の最後尾の布陣になっていたと思われる。
長束正家と長宗我部盛親は、この様に、毛利の動向を合わせる形で、〝不戦〟という結果になったが、毛利の事情と異なるところは、事前に家康に内応がなされておらず、戦わずして敗軍の将となり、逃走を余儀なくされたのである。
長束正家は、伊勢ルートを通り、居城水口城にたどり着いたが、家康方の池田長吉に攻められて自害をして果てている。
長宗我部盛親は、伊賀から大阪に入り、土佐浦戸にわたるというルートにて落ち延びた。
そして、井伊直政の仲介で家康に謝罪する為、大阪に向かう予定であったが、兄の津野親忠が藤堂と結んで東軍に通じており、戦後土佐半国を与えられる事になっている事を家臣から聞き、殺害していた事が家康の逆鱗に触れたのである。
井伊直政の取り成しにより、何とか死罪は免ぜられたものの、領国は没収され、盛親は牢人の身になったのである。
そして、安国寺恵瓊は、戦に敗れた今となっては、三成と謀り、毛利輝元を担ぎ出し、戦を企てた首謀者として犯罪人となっている。
毛利秀元は、輝元や毛利の安泰の為に、罪を全て一人で被る事になった恵瓊に同情して、陣所に匿った後、秀元率いる毛利本隊と共に、伊吹山中にに入らせ、佐和山近くにて密かに逃がしている。
恵瓊は、琵琶湖を渡り、坂本から山城国に入り、五十人余りの家臣と共に、大原に潜んだ後、鞍馬の月照院に隠れた。その後、一向宗門、端之坊に隠れたのち、彼が住持を務めていた東福寺に入ろうと輿に乗って夜逃したところ、六条辺りで奥平信昌の配下の者に捕えられた。
その時、恵瓊のもとには下人数名が残っていたのみであった様である。
その後、石田三成、小西行長と共に、六条河原で斬首され、首を晒された。
秀元は、決戦当日は南宮山に留まり、翌朝に南宮山を下り、伊吹山に入り、恵瓊を逃がした後、佐和山城攻撃している東軍の横をすりぬけ、近江八幡に宿営した。
秀元は、自軍が敗軍でないという自負のもと、伊勢街道の敗走ルートでなく、近江ルートを選択している。
翌日、瀬田の唐橋の手前に陣所に、福島正則と黒田長政が二人の陣所に赴く様に勧めてきた。
秀元は、陣所には赴くも、輝元の為に東軍に加わる要請は、きっぱりと拒絶し、「我、大阪の輝元の陣代なれば、速やかに大阪に引き上げるのみ」と言うと、長政の手を握ったまま陣外に退出したという。
秀元は、この様に、東軍に繋ぎ止められる事無く、近江ルートを貫き、淀から大阪に戻ったのである。
◎毛利の誤算
関ヶ原で戦いが行われていた時、大阪城の西の丸の毛利輝元も、南宮山の毛利軍と同様に動かなかった。
関ヶ原の敗戦は直ぐに輝元の許に届いた。毛利軍は殆んど無傷であり、輝元のもとには秀頼が居る訳で、秀頼を奉じて出陣するか、天下一の巨城である大阪城に籠城すれば、逆転とはいかないまでも、戦乱は長期化し、史実より毛利は有利に講和交渉を進めれたと思われる。
大阪に戻った毛利秀元や、大津城攻略から戻った立花宗茂は輝元に籠城戦を勧めている。
実は、秀元が大阪に戻った日の二日前、吉川広家が取り成し、家康サイドより福島正則・黒田長政を通じて、家康に忠節を尽くす事を条件に、輝元無罪と領国安堵の旨が伝えられていたのである。
輝元は、早速、正則と長政に礼状を送っている。合戦の前に、広家が取り付けた本多・井伊の誓書にある様に事が運んでいると安心しきっていた。
本多忠勝と井伊直政が輝元の責任不問と領国安堵を条件に、輝元の大阪城撤退を求めると、輝元はあっさりと退去したのである。
家康は、毛利との戦争を避け、輝元を豊臣秀頼から引き離す事に成功した。西の丸に入った家康は、輝元に重臣を人質に出す事や自軍を率いて島津を討てと命令して、従わねば、毛利秀就に対面せぬと強く出てくる。
更に、輝元が家康を糾弾する輝元の花押のある回状を発行したり、四国に軍勢を送っていた事が発覚した為、その責任により、毛利家の改易し所領全て没収の処分を伝えてくる。
家康が輝元を咎めた理由は、家康得意の言い掛かり的なもので、南宮山の兵を動かさず、大阪城を立ち退いた事で、その責任を問われない筈であった。 家康は、輝元が三成や恵瓊に担がれ仕方なく総大将になった事が広家との密約の大前提であるとして、約束を反故にしようとしたのである。
驚いた広家は、毛利家改易を避け、毛利存続の為に奔走し、広家の功労により与えられる筈であった周防、長門の二国 を毛利に与えられる様に懇願し、受け入れられる。 家康は、周防長門二国を輝元とその嗣子秀就に与える誓書を与えた。
しかし、秀就の居城は、交通の要衝に築かせず、山陰の萩に追いやり、豊臣への忠義に篤い福島正則と毛利の要塞と情報収集の役目を担う吉川広家を周防と安芸の境の要所である岩国に配置するという念の入れ様で、毛利に警戒している。
広家は、岩国に三万石を与えられたが、結局出雲富田十四万石からの減封になったうえ、大名でなく毛利の家老に留められる。 毛利家の家臣からは、毛利の領地を減らした張本人として冷ややかな目で見られたが、何はともあれ輝元が天下に色気を出した代償を最小限に留めた。
ただ、広家も輝元も家康を甘く見すぎていた事は誤算とい言えよう。
◎関ヶ原の戦い、傍観の代償
家康は、関ヶ原の戦いで毛利軍を動かさなければ、輝元の無罪と所領安堵をすると言う、吉川広家や毛利輝元との約束を反古にして、毛利の全ての所領を没収すると通達してきた。
広家の嘆願により、自身に与えられる予定の周防・長門の二ヵ国が輝元と六歳の嫡男、秀就に封じられたのである。
こうして、毛利百二十万五千石は周防・長門三十六万九千石に激減され、広家も出雲富田四十四万二千石の大名から周防岩国三万石の家老に格下げの格好となってしまったのである。
以前、大河ドラマ、天地人にて、関ヶ原の戦いの後、上杉家が、百二十万石から四分の三もの領地削封の為に、多数の家臣を抱えて貧困に苦しむ様が描かれていたが、毛利家も、全く同じ状況に直面している。
石高が減る事による減収だけでなく、実は、毛利八ヵ国のうち、没収された六ヵ国の年貢米は、既に 収納しているので、その分を新領主に返済せねばならないのであった。
検地を行い、貢租地を拡張して、五十三万九千石を弾き出した。
あとは、新田開発、新しい産業の奨励であるが、結局は、増税に頼らざるを得ず、四公六民だったのが、七公三民に迄に急増して、領民の不満が爆発し、周防山代一揆が勃発したのである。
更に、江戸城、駿府城などの普請の労役を課せられて、財政はさらに逼迫した。
上杉や毛利は、大幅に減封されたが、少なくとも大名には踏み留まれたのに対して、戦わずして、二十四万石の全てを没収された長曽我部盛親は牢人となり、厳しい監視の下、法体姿となり寺子屋の師匠に身を窶していた。
四国の雄、元親から家督を継いでわずか一年で、牢人となり苦渋を味わう事になったのである。
安国寺恵瓊は既に、斬首され、領国没収、長束 正家は水口城篭城の後に自害し、領国没収と言う様に、南宮山の傍観軍には、悉く、厳しい処遇が待っていたのである。
◎徳川幕府の圧力と毛利・吉川の苦難
家康は、外様の大名のうち、島津と毛利には 特に神経を使ったと思われる。
家康は、豊臣七将の中で、勇猛果敢な攻撃で西軍に立ち向かった福島正則への功により、安芸四十九万八千石を与えた。
正則を尾張清州という交通の要所から上手く追い出し、二倍強の領国の大名に抜擢して、ご機嫌を取りつつも、所領の三分の二を没収されて不満の募る、毛利の東の抑えとして配した。
正則は、大幅な加増に気を良くして、毛利への睨みを利かせ、不穏な動きでもあれば、家康に報らせると共に、迎え撃つ態勢にあった。
家康は、家康二男である、松平秀康の娘を十四歳になった毛利秀就に嫁がせ、松平姓を名乗らせている。その他、毛利元就以来続いていた朝廷や公家との結び付きを認め、特権を許した。
その一方で、領国の中心地に築城を許さず、萩城に追いやり、江戸城、駿府城築城、大阪城の修復の普請を手伝わせ、輝元が生きている間に限っても、十八回の賦役が命ぜられ、一回に付き五万両ほどの出費を強いられている。
知行削減に加え、労役と窮乏により、長州藩内では不満が爆発する寸前であり、長州藩の年始の挨拶は、「今年こそはやりまするか」「いやまだ早かろう」という、討幕の密談がされていたという。
また、長州藩士は、西枕で寝て、家康に足を向けたという。
しかし、財政難により力は削がれ、実行に移す事は出来なかったのである。
さて、関ヶ原の戦いにて、家康に内応する事で毛利の大名存続を図った吉川広家にも苦難は降り掛かる。
毛利輝元が石田三成の要請を受け、西軍の大将になった時点で、家康の毛利潰しの肚は決まっていただろう。合戦直前に、広家を使って打った〝内応〟という一手により、毛利の窮地を救った立役者である。
しかし、毛利宗家からは、毛利を没落・衰退させた張本人として、白眼視される。「あのまま、西軍として戦っていたら・・・」という思いが、毛利と吉川の溝を深めていた。
合戦後、吉川広家は領国経営に没頭する。とはいえ、出雲富田、十四万石から僅か三万石の岩国への減封、しかも、毛利家の家臣として分封される形である。
広家は、岩国に入ると、その地形を利用して、海抜二百メートルの横山に岩国城を築き、山の三方を迂回して流れる錦川を外堀として、南の山麓に、居館を造る事にした。
築城と同時に、町づくりにも追われる。何せ、千数百という数の出雲時代の家臣とその家族の殆んどを伴ってきている為、一万余りの人の住まいと生活の糧を確保する必要があった。
川を堰き止め家臣・町人の住む町を造り、道を設け、堤防を築き、食糧不足を補う為、海を干拓して農民の住める土地を造り、新田開発をする。また、製紙などの産業を興し、奨励している。それは、大変な苦労があったと記録に残っている。
1608年に、岩国城が完成し、城下町づくりは軌道に乗ったと思われたが思いもよらぬ事が起こった。1615年に幕府により発令された『一国一城の制』である。
広家は、命令発行に先立ち、家康より他の幾つかの藩と共に、特例として認める話が出来ていたが、毛利輝元は、あくまでも広家に城の破棄を命じ、広家は、その年の十月九日に、城の取り壊しに掛った。
吉川家は、その後も大名復帰を願い出るが、家老に留め置かれ、毛利宗家とは、ぎくしゃくした関係が続いたのである。
◎関ヶ原から大坂の陣へ
家康は、関ヶ原の戦いの戦後処理を終えると、秀吉と同じ関白の地位でなく、朝廷の権威から独立できる将軍職に就き、幕府を開き、その2年後に秀忠に征夷大将軍の位を世襲させている。
それは、秀頼が元服すれば、政権は豊臣に返還されるとの豊臣方の思いを打ち砕くもので、今後の政権は徳川家により継承する事を宣言するものであった。
関ヶ原の合戦後の豊臣家は、摂津・河内・和泉の三ヶ国六十五万石の一大名に過ぎなくなっていたが、太閤の世嗣の肩書、天下の大坂城、莫大な財力を背景に、徳川に臣下の礼を取る事なく、自立していたのである。
家康も、最初は孫の千姫を秀頼に嫁がせる、高台院や加藤清正らを招いての宴の開催、秀吉の七回忌に豊国社臨時祭を主催する等の気遣いを見せている。
これは、その時点では豊臣方が徳川政権に従順で無かった事に加え、関ヶ原の戦いで功を上げた、太閤子飼いの大名・豊臣恩顧の大名の力を衰えさす事が出来なかった事を意味している。
家康は、これらの大名と豊臣家の財力を削減する策に出る。
江戸城造営には、浅野幸長、池田輝政、福島正則、加藤清正、加藤嘉明、鍋島勝茂、片桐且元、島津忠恒、毛利輝元、ら30名に石材の運搬と材木の搬出を命じている。
何れも、豊臣恩顧の大名や西国の外様大名ばかりである。各大名は、石材運搬船を2年掛りで用意したり、嵐による沈没等の危険に晒されながら、石を運んだり、領内より江戸に人足を遣わせている。
各大名には、普請手伝いの費用が拝領されたが、とても、それで賄えないどころか、それ以上の負担をして、忠義の程を示さなければならなかった。
毛利輝元は、人足を相場の2倍半の人数を遣わせたり、家臣を京や堺で金策に走らせている書状を伊豆の石切り場の責任者に送っている様に、他大名以上に家康に忠節を示す事に気を遣っている。
薩摩の島津忠恒も同様で、石材運搬船を薩摩から回漕させる際、父義弘から 時節が遅れぬ様 油断を禁ずる書状を受ける等、家康に神経を使っている様子が窺える。
家康は、秀忠に将軍職を譲ったのち、駿府に隠居の形を取りながら、大御所となり力を揮ったが、この駿府城をはじめとして、大坂方に備えて次々と築城された彦根城、丹波篠山城、膳所城、伊賀上野城、姫路城、和歌山城などが、天下普請として、豊臣恩顧の西国大名に手伝い普請を命じている。そして、更に続いて家康の九男、義直の居城である名古屋城の築城である。
これには、丹波篠山城の普請を終えたばかりの池田輝政、福島正則、浅野幸長も重ねて命ぜられ、福島正則は加藤清正に不満を漏らしたと言われる。
これらは、大名に課せられる国役とされ、石高により割り当てられて動員する人夫の賃金、往復や滞在中の経費の全てを、大名が負担する形となっていた為、大名には多くの負担がのしかかった。
この天下普請は、大坂方に付く可能性のある大名の財力を削減させ、軍資金を使い果たさせるどころか、各藩の財政をも逼迫させた。
こうして、家康は、豊臣恩顧の大名の財力を削ぎながら、大坂方に備える包囲網ともいえる城を完成させていったのである。
家康は、さらに、大坂城内に莫大に残されている太閤の残した資産が、淀殿・秀頼親子の幕府に対する強気の姿勢に繋がっていると考え、故秀吉の冥福を祈る為の、豊臣家による寺社の造営や修復を奨励している。実際に、関ヶ原の戦い以後の七年の間に、実に、畿内一円の六十六件の造営が豊家により行われている。
そして、山城国東山の方広寺の大仏殿の建立も、家康が勧めている。秀頼は、家康の支持を受け資材の調達費用として、千枚吹きの分銅金十一個と二千枚吹きの分銅金十七個を送り、小判三十九万七千六百六十両の建設資金となっている。
方広寺は秀吉創建の寺院の為、施主は秀頼であったが、大工の棟梁は家康側近の中井正清と五右衛門であり、秀頼に法外の金銀を遣わそうという家康の意図が見える。
しかし、大坂の陣にて膨大な資金が使われたにも拘らず、大坂落城後に焼け出された金二万八千六十枚、銀二万四千枚と言う記録が示す様に、こちらは家康の考えが及ばない程の財力が有った為、財政を困窮させる事は出来なかったのである。
そのかわり、この大仏と共に、方広寺に鋳造されたの梵鐘の銘文と棟札が豊臣潰しの口実になった訳なので、この大仏建立は結果的に家康の目的を達したといえる。
◎関ヶ原牢人
天下分け目の関ヶ原の戦いにより、毛利や上杉をはじめとする減封処分にあった五大名の他、多くの改易大名とその家臣である〝関ヶ原牢人〟が大量に出現したのである。
全ての領地を没収されたのは、本戦参加の石田三成(斬首)の近江佐和山十九万四千石、小西行長(斬首)の肥後宇土二十万石、宇喜多秀家(八丈島流罪)の備前岡山五十七万四千石、大谷吉継(関ヶ原にて自害)の越前敦賀五万石、戸田勝茂(戦死)の越前安居、平塚為広(戦死)の美濃垂井、
西軍に属しながら南宮山にて傍観していた長宗我部盛親の土佐浦戸二十二万二千石、安国寺恵瓊(斬首)の伊予大野六万石、長束正家(居城にて自害)の近江水口五万石、
京極高次の大津城攻撃を攻撃した、立花宗茂の筑後柳川十三万石二千、毛利秀包筑後久留米十三万石、宮部長煕(仏門)の因幡鳥取二十万石、
親子・兄弟で東西に別れた真田昌幸(九度山蟄居)の信濃上田三万八千、前田利政の能登七尾二十一万五千石、
米野の戦いにて福島正則らに敗れて岐阜城開城した織田秀信(高野山にて仏門)、大垣城を主将として守備をした福原長堯(伊勢朝熊にて自害)の六万石、同大垣城守備の氏家行広の伊勢桑名二万五千石、丹羽長重(江戸品川に蟄居)の加賀小松八万石、
三成挙兵に応じながらも、家康とも内通していた増田長盛(高野山追放)の大和郡山二十万石、本戦にて小早川秀秋の裏切りに続いて家康に寝返った赤座直保の武蔵岩槻二万石、小川祐忠の伊予今治七万石も没収されている。
家康に反抗した大名への処分は、殊の外 厳しく、真田親子の様に赦免嘆願するも、許されず、徳川の世が確立をしていくに従い、領地回復の機会は遠退いて行った。
西軍として戦った大名で、関ヶ原の戦いの後、改易後に大名に復活できたのは、四年の牢人生活の後にその軍才を秀忠に認められ、豊臣方に味方される事を回避する為に奥州棚倉藩一万石にとり立てられた立花宗茂(後に柳川藩主に返り咲く)と、やはり秀忠にその博学を認められた丹羽長重が常陸古渡一万石を与えられた位である(後に棚倉・白川城主となり、秀忠側近となる)。
その他の西軍に属した大名の家臣の多くは、牢人となり、その数の多さに対し仕官の口は限られ、仕官出来た者は ほんの一握りであった。
又、長宗我部氏の旧領地に入った山内一豊の例に有る様に、石高の増加に伴う家臣の雇い入れをする際、旧領主の色を消す為に長宗我部の家臣の仕官を拒絶したり、家康の顔色を窺って関ヶ原牢人を雇うのを敬遠した事情があったのである。
改易された大名の多くは、他大名の預かりの身になったり、蟄居、出家、隠遁生活を送っており、真田幸村の様に兄からの仕送りや長曽我部盛親が寺子屋の師匠をしつつ、他家に奉公が叶った旧家臣からの扶助を受け取りひっそりと暮らしていた。
主家改易以来牢人していた者、仕官先での折り合いが悪くなり主家を変えた事による奉公構に遭った者は、具足、槍、馬に従者を従え、身上を稼ぐ為に 各地を流浪していたのである。これらの者にとって、東西の手切れの時こそが、武名を挙げ、捲土重来を期す、最大にして最後の機会になる。
家康は、方広寺鐘銘の件の釈明する為に、駿府に赴いた片桐且元に、大坂方が牢人を駆逐しようとしている事を咎めている。これは、豊臣家への挑発であり、豊臣が徳川方に対し、徹底抗戦する事も、その戦力の中心が牢人衆となる事も、想定内であった。むしろ、そうなる事で、豊臣と牢人たちを一気に片付け様としたのであった。
◎五人衆 大坂城入城
東西の手が切れると、秀頼は、太閤の残した金銀を振る舞い、各地に潜んでいた牢人達を集め始めた。徳川政権下で地位と領国が確保されている大名たちは、一人として招集に応じなかったのに対し、牢人達は、続々と入城する。彼らは、地位も領国や奉公先も失い、それを挽回する機会も無く、15年の歳月を過ごして来たのである。
先ず、最初は、白地に花クルスの旗を翻して、八千のキリシタン武士を引き連れて入城した明石全登である。関ヶ原の戦いでは宇喜田秀家隊の先鋒として、福島正則と激闘を繰り広げている。黒田長政の説得により戦場を離脱し、黒田領に匿われた。彼は、徳川がキリシタン弾圧に動いた事に反発して、入城を決めている。
毛利勝永は、父である森勝信が秀吉に気に入られ、毛利姓を賜った経緯があり、、関ヶ原の戦いでは、父子共に西軍に加わり、伏見城を攻撃している。戦後、加藤清正、次いで土佐にて山内一豊預かりの身になっていたが、商人を装った秀頼の家臣、家里伊賀守により大坂召募の密旨を受け、大坂に赴いている。
その、土佐の旧領主であった長宗我部盛親は、京の相国寺門前に主従六人で、幕府側の役人の監視のもと、蟄居させられていた。盛親には、豊臣から密かに仕送りがされており、各地に潜んでいた五千もの旧臣を引き連れて、乗り込んでいる。
真田幸村も、九度山にて浅野長晟の監視下におかれ、蟄居させられていたが、秀頼の使者により大坂入城の誘いと共に、黄金二百枚と銀三十貫が届けられた。幸村は、武将として待ちに待った活躍の場を得て、意気揚々と大坂に向かう事になった。
後藤又兵衛は、黒田長政の家臣で、大隈一万六千石を預かり、主君を超える程の天下の名士として名を馳せていたが、それが二人の間の確執を深めており、長政の父如水が亡くなって仲を執り成す者が居なくなり決別している。その後、細川忠興に身を寄せ様としたが長政が横槍によりなせず、その後の仕官も長政による奉公構えにより叶わなかった。六条河原に乞食小屋に居たところ、大坂方の招きを受けて入場したのである。
この五人衆の他には、又兵衛同様、加藤嘉明の奉公構えに祟られ、諸国を流浪した後、京都妙心寺の雲水となっていた塙団右衛門、そして、関ヶ原の西軍関係では、父大谷吉継と共に関ヶ原に参戦した後、諸国を流浪していた大谷大学、大谷隊で戦い、討ち死にした平塚為広の遺子である平塚左馬助、関ヶ原で大垣城を守衛した後、若狭・播磨にて閉居していた氏家行広、東軍の父と分かれて西軍に与した仙石秀範は、戦後、長宗我部盛親と同様に京にて手習いの師匠をしていた。これに、木村重成、大野治長・治房、薄田兼相をはじめ、秀頼直衛隊である七手組等の在城の武将や豊臣家臣が加わり、総勢十万に膨れ上がったのである。
牢人の中には、幕府より招かれたり、関東方への従軍の誘いが有った者も多かった様であったが、徳川の大軍勢のなかで、小さな功をあげて小禄に預かるより、豊臣方にて一軍の将として迎えられ、大きな功名と武名を上げ得る方を選んだ者が殆んどである。
それは、武士の本懐を遂げれるという反面、破滅への道であった事は承知の上の選択であった。
◎大坂冬の陣おける豊臣恩顧の大名の身の振り方
大坂の陣において、全ての大名が家康に従っている。
何せ、豊臣恩顧の大名においても、加藤清正、中村一氏、堀尾義晴、浅野幸長は亡くなっており、存命の武将達も、家督を息子に譲ったり、徳川政権下で、領国経営が軌道に乗ってきた所であった。
戦乱の世は終わり、戦乱により命や領土を失うリスクは無くなり、徳川に逆らっているとの誤解を受ける事が無い様に気を配れば、領地と大名の地位は安泰でいられるのである。
豊臣恩顧の大名の筆頭であった福島正則でさえ、
秀頼の援護依頼の使者との面会を拒んでおり、親書をも受け取らなかった。
それでも、福島正則は加藤嘉明、平野長泰、黒田長政らと共に、江戸留守居役を名目本多正純から江戸留め置きを申し渡された。大坂の陣では、秀頼から遠ざけられていたのである。
家康は、万一に備え、彼らを信用していなかった。
その万一とは?
現時点では、大坂方の敗北は ほぼ確定的で、大坂城に入る事は大名の地位や領国など、一切のものを捨てる事になる為、先ずは、その様な真似はしないと思われた。
しかし、家康は、大坂の陣の時に 齢七十三歳であった。
当時の寿命からすると、かなりの高齢であり、いつ病に伏したり、お迎えが来てもおかしくない年齢である。
実際に、方広寺鐘銘事件をみても、大坂方に因縁を付けた様なもので、〝鳴く迄 待とう〟の家康とも思えない、強引で事を焦ったやり方をしている。
年齢的に焦りがあったと思われる。戦の最中に家康が急に亡くなった場合は事情が大きく変わってくる。それまで、家康には渋々服従していた大名も、この期に、次々と反旗を翻さないとも限らない。
この場合に備えて危険分子は遠ざけておく必要性があった。この、万一の家康の病、及び死亡の場合に賭けて、豊臣方にも布石を打った大名がいた。
関ヶ原の戦いで、東西両軍に二股をかけ、戦わずして領国を四分の一にされた毛利である。しかも、その後、泰平の世に移り変わろうとしているため、領地回復の機会は、確率は低いとはいえ、東西の手が切れるその時しかないからである。
毛利は、大坂の陣において、基本的には家康に従いながらも、密かに 関ヶ原の戦い 同様の二股作戦に出るのである。
◎大坂の冬の陣においての毛利の日和見
大坂の陣において、殆んどの大名は現在の地位を守る為に江戸方についており、牢人になっている者が大きく地位を挽回する為には、斜陽の豊臣に賭けるしかなかった。
彼らを一軍の大将として扱ってもらえるのは、大坂方しかなかったのである。
大名の中でも、隙があれば、大きく地位を挽回する機会を窺っていた者がいた。関ヶ原の戦いで領地を四分の一に減らされて以来、天下泰平の世になった事で、領地奪回の機会が巡ってこなかった毛利である。家臣にも、不満と幕府への反抗心が募っていた。
毛利にとっては、豊臣と徳川の手切れは、危険ではあるが、今後しばらく訪れないであろう大老の地位と領地奪回の機会であった。
表立っては江戸方に付きながらも、密かに大坂方に一手を打っている。
毛利家の重臣、内藤元盛が粟屋元種と共に大坂入城をしている。家臣を引き連れ、軍資金五百両と兵糧一千石を持参していた。牢人を装ってはいたが、前当主毛利輝元と当主秀就の内旨を受けての入城であった。
情に厚かった毛利輝元の豊臣へ恩返しとも、関ヶ原の戦いにて大阪城にてお守りをした、秀頼公を思いやっての行為であったとも言われているが、明治以降に長州の藩祖を持ち上げて作られた話であり、露見すれば即改易という大きなリスクを冒してまで、豊臣に忠誠を尽くしたとは思えない。
輝元は、養子の秀元と密談をし、高齢の家康の急病・急死に備えて大坂方にも近付いたのが真相と思われる。合戦中に家康にもしもの事があった場合、江戸に留め置かれている福島正則、加藤嘉明をはじめとする豊臣恩顧の大名や徳川に不満を持つ大名が秀頼の元に集まる事を想定して打った一手であった。
豊臣家に、それなりの顔の立つ者として、毛利元就の曾孫で輝元と従兄弟の関係にある元盛が任命されたのである。城内にて密命を果たす事、お互い通じない事、大坂方敗戦の折は、内藤の本家・分家の将来をとり立てるとの約束が交わされていたという。
毛利家自体は、徳川方に与して、冬の陣で秀元は毛利の先遣部隊として奮戦しているが、当主秀就の本隊は、出陣中の輝元の病を理由に西ノ宮より先には進軍せず、家老の福原・児玉の支隊も、風待ちを理由に兵庫港に停泊したまま動かなかった。
まるで、関ヶ原の戦いの時の南宮山の傍観を思わせるような光景であった。
◎大坂の陣終結
大坂冬の陣は、真田幸村の奮戦も及ばず終結し、大坂方不利となる条件で講和が結ばれた。
講和の条件にあった、大坂城の外堀だけでなく、徳川方によって内堀も埋めたてられて、大坂城は 丸裸にされた。
家康は、いよいよ総仕上げに 掛かった。
大坂方が壊れた塀を直し、埋められた堀を掘り返した事を大坂方謀反の意ありて、戦に備えていると言い掛かりをつけて、秀頼に国替えを迫った。
大坂方は、これを拒絶して、大坂夏の陣が勃発し豊臣滅亡へと動いていく。
こうなると、豊臣の敗北、滅亡は疑う余地が無くなり、さすがの毛利も、冬の陣の時の様に日和見という訳にはいかず、夏の陣は、秀就と秀元が出陣して、病を押して輝元自らも戦に出向いている。豊臣政権下での執権に返り咲く夢は消えるどころか、旧主豊臣に刃を向け、その滅亡を見届ける羽目になったのである。
真長宗我部盛親は、関ヶ原の戦いで土佐一国を失っており、その奪回をかけて、全国に散らばっていた旧臣を集めて大阪城を発ち、八尾にて藤堂隊と激突した。
藤堂高刑の別働隊の左翼には、土佐領主時代の家老であった桑名弥次兵衛がおり、くしくも、かつての主従の対決となった。
関ヶ原の戦い後、盛親の家臣のうち、弥次兵衛ほか十九名が藤堂家に召し抱えられており、皮肉にも弥次兵衛はかつての主君の為に、密かに仕送りをしていた間柄でもあった。事情を知らぬかつての家臣が恩知らずと罵るものの、弥次兵衛は覚悟を決めており討ち取られている。
長宗我部隊は、藤堂隊を潰走させ、藤堂高刑の首を取る戦果を上げるものの、局地的な勝利にとどまり、同日の戦いにて、木村重成は井伊直孝隊と奮戦の末、敵将、庵原助右衛門の槍にて命を落とし、後藤又兵衛も真田・毛利軍と合流する予定を濃霧に阻まれ、道明寺・小松山で単独で東軍の水野・伊達・本多勢に挑むも、敵の銃弾に倒れるなど、秀頼のもとには、味方の武将の討ち死の報がもたらされる。
その直後、道明寺の戦いにて、大坂方は抵抗をみせるも、薄田兼相 が戦死、後藤隊・薄田隊の残党が誉田村に後退し毛利隊に吸収され、北川宣勝の救援に向かっていた真田勢の到着を待ち合流する。
翌日の五月七日、天王寺にて東西決戦が行われたが、この時すでに、四月末に樫井の戦いで戦死している塙団右衛門、木村重成、後藤又兵衛、薄田兼相等の大将級の武将を欠いている。
真田幸村は、自ら緋縅の鎧を纏い、具足・旗指物・陣幕に至るまで朱で統一した、〝赤備え〟軍団を率いて茶臼山に陣を張っていた。毛利勝永が天王寺の南門側に陣取り、後方に大野治長の本隊が、別働隊で明石全登、篠山麓に北川宜勝、岡山口に大野治房と御宿政友を布陣させ、秀頼の大阪城よりの出陣を待つ形を取っていた。
秀頼の出陣が遅滞している時、家康の大軍勢が天王寺口に進軍しているとの報がもたらされていた。東軍は家康の軍令に背いて先駆けを逸る松平忠直隊を毛利隊が衝き、隊が乱れ隙に真田隊が家康目指して突進し、家康の手薄となった後備につけ込もうとした。
真田幸村は、追い詰められた大坂方の活路見出す為に、〝家康の首〟を取る事のみを考えた戦いを展開し、家康をあと一歩のところまで追い詰めるも、奮戦の末に力尽き、戦場に散っている。
大坂方は、牢人衆が奮戦するも、秀頼の出陣はいたらず、秀頼直衛隊である七手組ほか豊臣譜代の家臣による後陣の戦意・戦力が見劣りし、勝負所に一気投入する事が出来ず、敗北が決定し、ついにその日の夕刻には大阪城が落ちたのである。
秀頼と淀殿の助命嘆願を、秀頼に嫁いでいた家康の孫千姫に託すも、受け入れられる筈もなく、切腹の上意が伝えられ、五月八日の正午ごろ、秀頼・淀殿は自害、大野治長・毛利勝永・真田大助・大蔵卿局らも山里廓の炎と共に消えている。